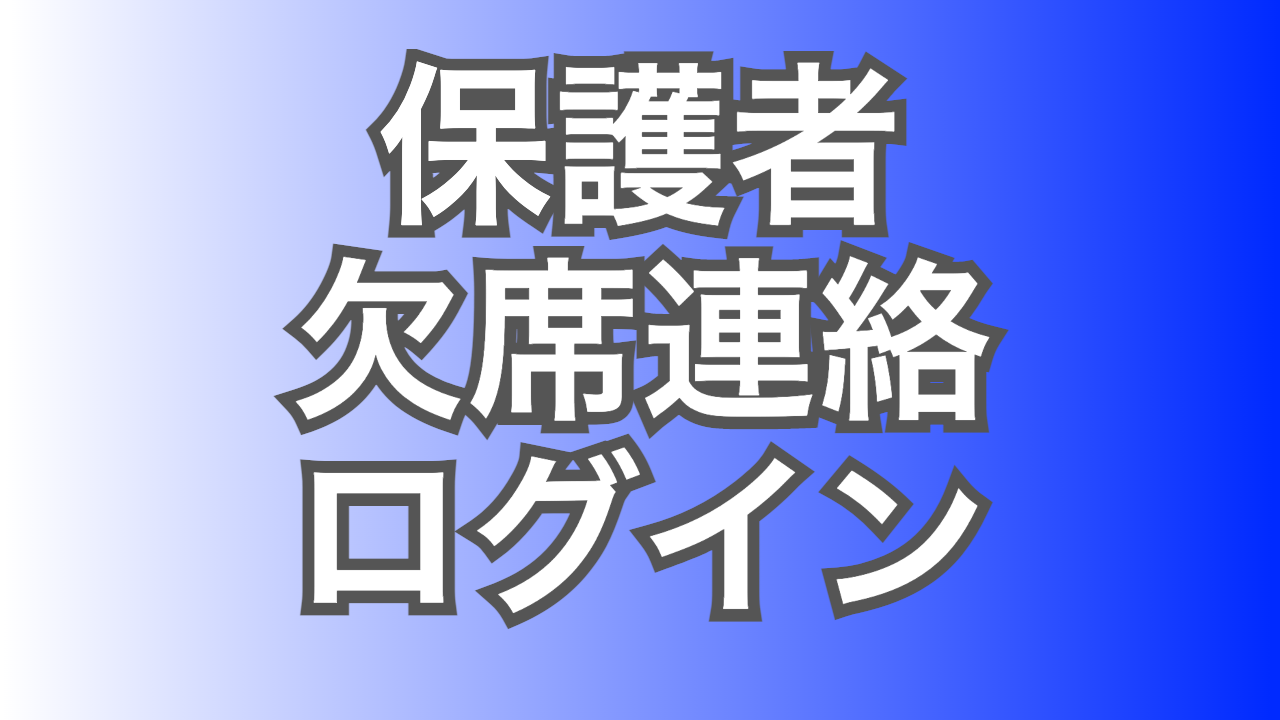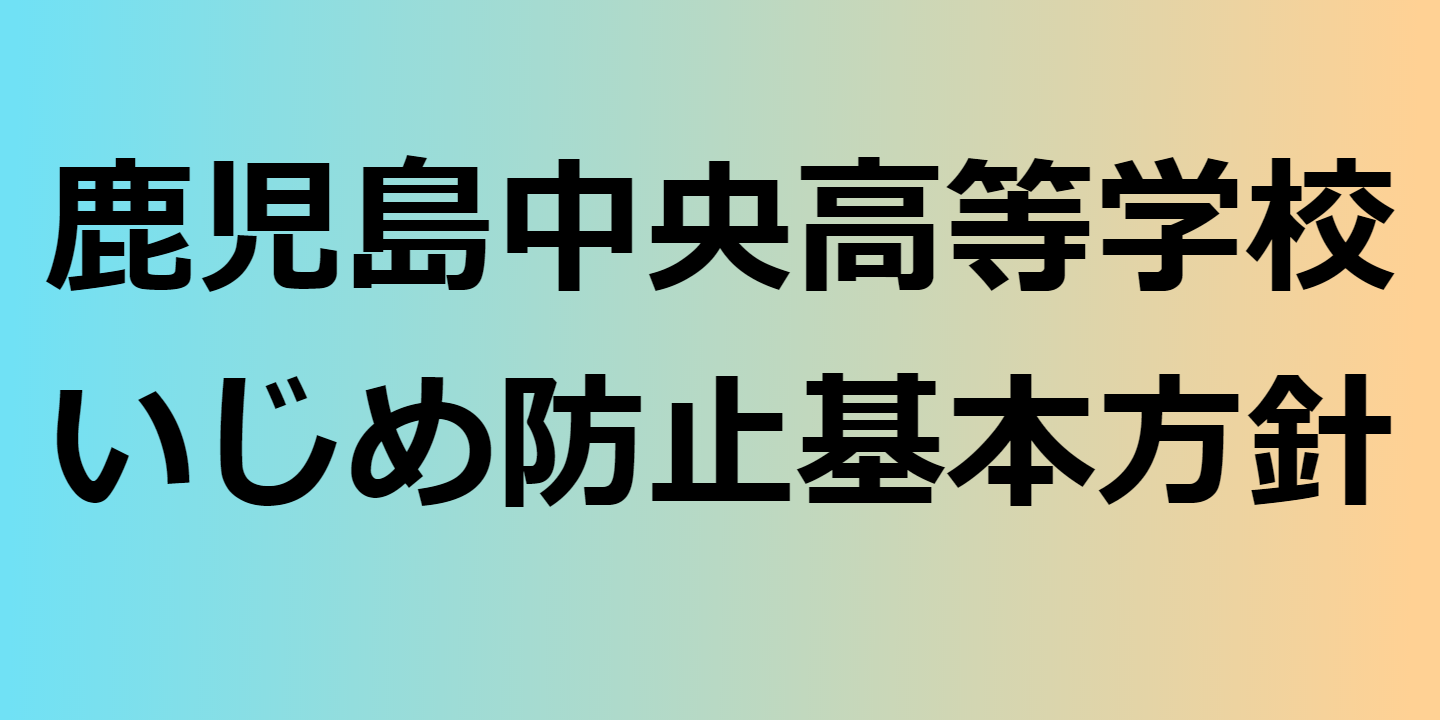分類
2015年12月07日(月)
第2回避難訓練
第2回避難訓練
6限目の授業終了直後に火災報知機を鳴らし,全校一斉に避難訓練を行いました。選択科目等でHRを離れている場合は,その場からの避難です。
化学実験室から出火との想定で,通報や連絡の確認,避難経路の確認,消火器の訓練,放送設備の点検等を行いました。団訓で普段から素早い移動には慣れていますが,いざという時を想定することは,大変重要です。実際の火災はいつ起こるかわかりません。現在講堂の改修工事中で避難経路が制限されていることも,今回の訓練の重要な課題でした。
もともと火を出さないことが重要ですが,万一の確認をすることが出来ました。
2015年12月04日(金)
講堂屋根工事中
講堂屋根工事中講堂は改修工事中です。
ここ数日の工事の様子です。
先日,屋根に防水シートが張られていましたが,その上にグリーンの鉄板が並べられ,全てきれいに覆いつくされました。
工事前と比べるとすっきりした色合いのように感じます。
工事は順調に進んでいます。2015年12月03日(木)
家庭クラブ保育園訪問
家庭クラブ保育園訪問
本日まで後期中間考査でした。その午後を利用して,1・2年生の希望者20人が「なぎさ保育園」を訪問させていただき,保育の現場を体験的に学ばせていただきました。
乳幼児への理解を深め,思いやりを持って接することや,子どもの発達と保育,子どもの福祉における地域及び社会の果たす役割について学ぶことが目的です。
最初に,園長先生から説明を伺った後,おやつ介助やふれあい活動などを体験させていただきました。
参加した生徒たちは,貴重な体験を通して様々なことを学ぶとともに,自分の将来について考える機会にもなりました。
御協力いただいた「なぎさ保育園」の皆様,ありがとうございました。2015年12月02日(水)
2学年PTA
2学年PTA
昨日から明日までの日程で1・2年生は中間考査,3年生は12月考査を行っています。
本日は,午後から2学年の保護者の皆様に御来校いただき,学年PTAを行いました。
進路指導部から学習への取組について,学年からは2週間後に迫った国内体験学習について御説明いたしました。
その後は各教室に入り,担任からクラスの状況等について説明しました。
中央高校での学生生活も半分を超え後半へ入ってきました。これからも保護者の皆様方の御理解と御協力をお願いいたします。2015年12月02日(水)
平成28年度入学者選抜募集要項 請求方法(12月2日掲載)
平成28年度入学者選抜募集要項 請求方法(12月2日掲載)
平成28年度入学者選抜募集要項等を掲載します。
・平成28年度入学者選抜 募集要項(一般入学者選抜)
・平成28年度入学者選抜 願書(みほん)
・平成28年度推薦入学者選抜 募集要項
・平成28年度推薦入学者選抜 願書(みほん)
・平成28年度推薦入学者選抜 推薦書H28-suisen-suisensyo.pdfをダウンロード
※推薦書については,下記のWord,一太郎のファイルもご利用ください。(両面印刷)
h28suisensuisensyoword.docをダウンロード
h28suisensuisensyoichitaro.jtdをダウンロード
・平成28年度帰国生徒等特別入学者選抜 募集要項
・平成28年度帰国生徒等特別入学者選抜 願書(みほん)以上の7点です。
日程は県教育委員会が定めた要綱のとおりです。
https://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/school/koukou/nyushi/28/index.html[願書等の請求方法について]
願書等が必要な場合は,中学校から本校教務係へ必要数をお知らせください。
次の(1)~(2)のいずれかの方法にて請求・受領してください。(1)本校に直接取りに来ていただく。
この場合,事前に電話連絡をください。
すぐにお渡しできるよう準備しておきます。
(2)本校へ必要部数を電話連絡し,郵送を依頼する。
例:一般選抜要項○部,一般選抜願書○部
推薦要項○部,推薦願書○部,推薦書○部
帰国生徒等要項○部,帰国生徒等願書○部※不明な点は,本校教務係までお問い合わせください。
<問い合わせ先>
鹿児島中央高校 電話099-226-1574 教務係2015年11月30日(月)
学校関係者評価委員会と学校活性化委員会
学校関係者評価委員会と学校活性化委員会
午後校長室で学校関係者評価委員会と学校活性化委員会を行いました。
年間三回実施する予定で,今回はその2回目です。
学校関係者による評価を取り入れ,自己評価の客観性・透明性を高めるとともに,学校・家庭・地域が一体となり学校の現状と課題について共通理解を深め,その連携協力による学校運営の改善を促進することを目的としています。各係から校務分掌評価と前期授業評価の報告を行い,委員の先生方との意見交換を行いました。
今後本校が取り組むべき課題について,生徒,保護者,地域の方々との関係,職員と生徒との関係性,生徒同士の関係など,多岐にわたる御意見をいただき,時間が足りなくなるほど充実した話し合いが出来ました。また,編集した団訓の動画もご覧いただき,多くの人に見ていただけるようにしてはとの嬉しいお言葉もいただきました。
これからの鹿児島中央高校がなすべきことについて多くの示唆を得ることが出来ました。ありがとうございました。
2015年11月30日(月)
学校だより「朝日子」第113号発行
学校だより「朝日子」第113号発行
H27-asahiko-113.pdfをダウンロード
学校だより「朝日子」第113号を発行しました。
保護者には生徒便で配布しました。
PDFファイルでもご覧いただけます。2015年11月30日(月)
進路指導室だより11月号発行
進路指導室だより11月号発行H27-11-shinrodayori.pdfをダウンロード
進路指導室だより11月号を発行しました。
保護者には生徒便で配布しました。
PDFファイルでもご覧いただけます。2015年11月27日(金)
講堂屋根工事中
講堂屋根工事中
講堂は改修工事中です。
現在の工事の様子です。
先日まで屋根部分は骨組みだけでしたが,木材の下地部分が張られ,また防水シートが張られ,見る見る変わってきています。
工事は順調に進んでいます。2015年11月27日(金)
職員研修(教育相談)
職員研修(教育相談)
放課後,職員研修として鹿児島大学学術研究院法文教育学域教育学系の有倉巳幸先生をお招きして,「青年期における行動の理解と支援」というテーマで講演をいただきました。
毎日接する生徒たちという「現代青年」の特徴について,友人関係づくりの特徴といじめ問題,高校生のネット依存,教育相談のあり方,など多岐にわたるテーマでお話しいただきました。
共感する聞き手としての教育相談の方法など,生徒との信頼関係をつくる,学ぶことの多い研修でした。